これは絵画と写真の違いについてアンリ・カルティエ=ブレッソンが語った時の言葉です。
絵画はリアリティに入念に手を入れて絵画が出来上がるのに対し、写真はただ1回の露光で捉えた究極の一瞬なのだ。と語っています。
アンリ・カルティエ=ブレッソンは絵画を見るのがとても好きだったようで、写真展に行く事よりも絵画展などの方へ積極的に足を運んでいたといいます。
「私は普通あまり多くの写真を見ない」と断言しているほど。
古い絵も現代の絵も好きで、絵画を見ることに多くの時間を割いていたそうです。
完成された構図を一瞬の世界の中に入れ込むことに執念を持っていたブレッソンの言葉らしいですね。
ブレッソンの写真を見ると本当にこんな瞬間があったのだろうか?と思わせるほど驚きの瞬間を撮影しています。
どうしたらこんな瞬間に出会えるのか・・・。
良くブレッソンは長いこと同じ場所に待ち続けて決定的瞬間を撮影したのでは?と言われていますが、あの有名な水たまりを飛び越える瞬間の写真以外では待ち構えての撮影はしたことが無いと話していますよね。待つこと無くあれだけの瞬間が撮影できたのは彼の体全体、五感全てが決定的瞬間を捉えるアンテナのような人だったのでしょうね。
それを証拠に、
「写真を撮るということは( 同時に、そして何分の1秒かの一瞬に) 真実そのものと、それに意味を与える視覚的に知覚された形態の苛酷な結びつきを認識することである。頭脳、目、心を同一軸上に結びつけることである。」とも話しています。
ここまでの言葉がスッと出てくるアンリ・カルティエ=ブレッソンってやっぱり凄いですね。
言われれば、確かにそうかと思いますが、この言葉を体で体得していた巨匠だったのでしょう。
「決定的瞬間」という言葉を生み出す人だけあります。
最後にもうひとつ。
アンリ・カルティエ=ブレッソンの若かりし頃の写真って見たことありますか?
ほとんど皆無だと思います。それはブレッソンが写真に撮られることを非常に嫌ったからですが、その理由は御存知ですか?
とにかく自然体での瞬間を狙うカメラマンだったので、名前が売れてからは顔が世に知られてしまうと撮影中に気づかれて自然な観察が出来なくなるから撮影を拒み続けたそうです。まさに空気のような存在で撮影していたのかも知れません。
|
|
アンリ・カルティエ=ブレッソン(Henri Cartier-Bresson、1908年8月22日 – 2004年8月3日)は、フランスの写真家。 20世紀を代表する写真家であると多くの写真家・芸術家から評されている。彼は小型レンジファインダーカメラを駆使し、主にスナップ写真を撮った。芸術家や友人たちを撮ったポートレイトもある。 彼はライカに50mmの標準レンズ、時には望遠レンズを装着して使用した。1947年にはロバート・キャパ、デヴィッド・シーモア、ジョージ・ロジャーと共に国際写真家集団「マグナム・フォト」を結成した。 |

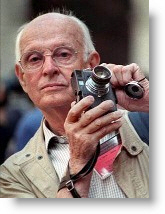

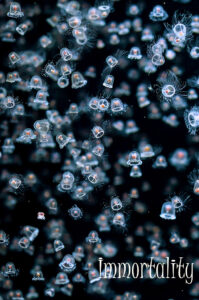

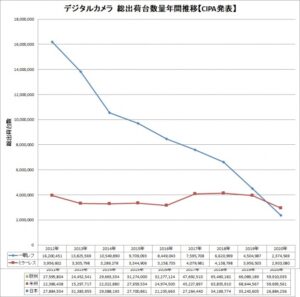




コメント
コメント一覧 (1件)
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
写真はただ1回の露光で捉えた究極の一瞬なのだ
この言葉の奥は非常に深いですね。
全く同じ画像を撮る事は不可能ですので、、、
そういった意味では、
やはり芸術の世界はものすごいものがありますね。
なんだか感動しました。